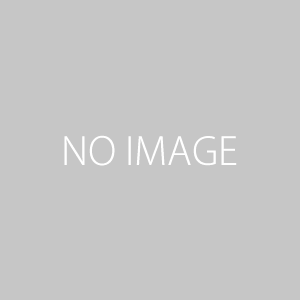
映画評
枢機卿達の根比べと「日本国天皇を選挙で選ぶ日」
毎度ながらの同居家族のご下命により、映画「教皇選挙」を鑑賞してきました。 https://cclv-movie.jp/ アカデミー賞の有力候補なのだそ...
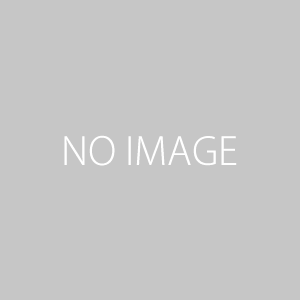
毎度ながらの同居家族のご下命により、映画「教皇選挙」を鑑賞してきました。 https://cclv-movie.jp/ アカデミー賞の有力候補なのだそ...
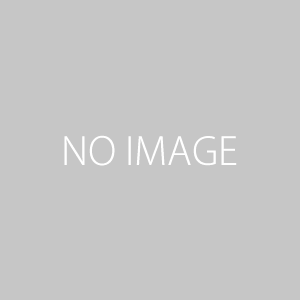
私は、初代ガンダムのTV放送(岩手)時は小学2~3年、人気絶頂の時期が小学4年頃でしたので、当時の二戸人なら誰もが知る「おもちゃのもとみや」に入り浸る...
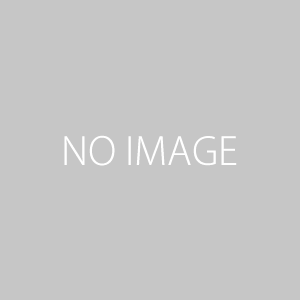
先日、宮崎監督の最新(最後の?)映画を拝見してきました。 ラピュタのような爽快で分かりやすい冒険活劇を期待する方には不満が残るかもしれませんが、トトロ...
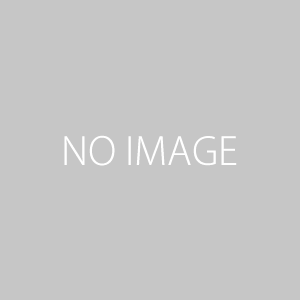
先日(11月25日)は三島由紀夫の命日(三島事件の勃発日)とのことですが、数ヶ月前、彼と東大全共闘の討論を収録した映画を拝見しました。 冒頭で、三島由...
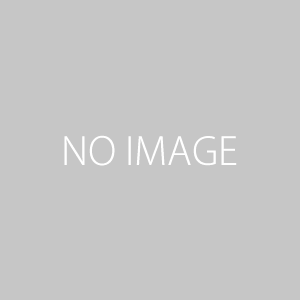
昨日、芥川賞受賞作を原作とする大友啓史監督の映画「影裏」の完成披露試写会が盛岡市内で行われ、とある事情により招待券をいただいたので、拝見してきました。...